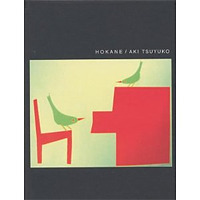
2006年発表、アキツユコさんの作品。KAWAIのエレクトーン、オルガン、ハープ、ヴォーカルなどで構成され、アルバム1枚を通して組曲のような音楽。尊敬する作曲家のおひとりです。

SNDのマーク・フェルのソロ作品、2010年発表。同時期にEdition Megoから『UL8』というアルバムも発表している。SND『ATAVISM』の流れはあるものの、常に更新し続ける鋭い音の質感とグリッドに気概を感じます。この電子音楽を日本の電圧で作る事はなかなか難しい。
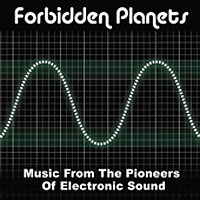
電気を使って音楽を演奏、再生、パフォーマンスする行為の起点がアーカイヴィングされた作品。電子音楽の名作を集めたものは数多いですが、1960年代前の楽曲が多く収録されています。ケージのFONTANA MIX、リゲティのARTIKULATION、BBCの放送用実験の音楽など、とてもユニークな2枚組。
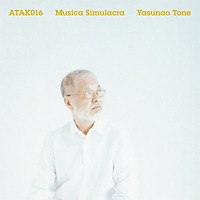
2011年発表。万葉集全首を電子音に変換した2000時間収録のCD-ROMとレーベル主宰の渋谷慶一郎さんが編集したCDなどが入ったBOX。強度なコンセプションとテクノロジーが重なった傑作。あらゆる側面のグリッチが入っていると思います。この偉業にリスペクトします。
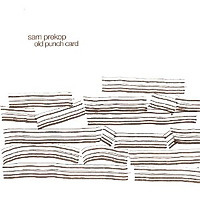
The Sea and Cakeのフロントマン、画家、写真家でもあるサム・プレコップの3rdソロ。再生するとバンドで聴ける愁眉なヴォーカルやギターは全く流れてこず、ひたすらシンセサイザーでモジュレーションされたサウンドが空間を満たします。古典的なミニマル・ミュージックの構造ですが、豊かでソフトな音質によって、僕は何度も聴いてしまいます。
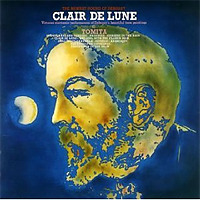
震災後にSonarSoundTokyoに出演させていただいた時、パフォーマンス前に大竹伸朗さんとICC学芸員・畠中実さんのトークがありました。その中で、ボソッと大竹さん「電気がなきゃ、エレキだって弾けないよねぇ。」と。僕が思い浮かんだ音楽が、なぜか冨田勲のドビュッシーでした。

レーベルDrag Cityの中にあるジム・オルークの再発専門レーベル「Moikai」からの作品。ラファエル・トラルがリマスター。実験、電子音やミュージック・コンクレートからの前衛部分とメロディカなどの音色のポップさが屈折無く交わります。2000年代以降にエレクトロニカと呼ばれるフレームは、ここに近しいと思います。
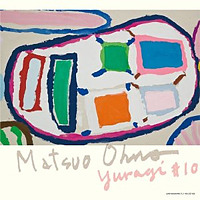
2011年発表。僕が「音響」という考え方を意識するようになったきっかけが大野松雄さん。HEADZからの新作。タージ・マハル旅行団の記録映画『旅について』の仕事も痛烈です。多くの事を学びました。リスペクト。











